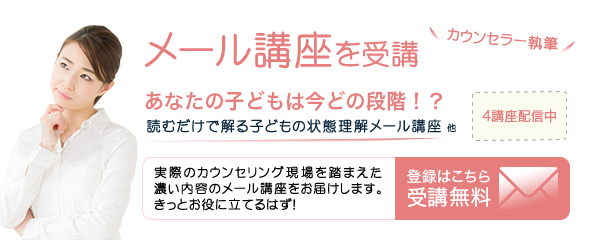【親子関係改善】新学期を見据えた子どもとのコミュニケーションのやり方
不登校支援センター大阪支部の佐久真です。
今回は、年越し・お正月という特別な雰囲気の中、親子で交わしたコミュニケーションやその雰囲気を、3学期からの親子関係にどう活かすのかについてお話したいと思います。

家族が集まる年末年始は、子どもだけでだらだらと過ごしたり家の中でテレビやゲームばかりしていてはもったいないということで、冬休みにしかできない子どもとの関わりや、子どもと一緒に学ぶことを意識される方が多かったと思います。
親子関係が良好であること
今、親子関係が悪くてなかなかコミュニケーションが取れなかったり、関係性が希薄になってきていたりする方々にこそ、このタイミングで親御さんの方から積極的に関わって、関係を良好に保つことを目標にしていただけたらと思います。
それはなぜか・・・
それは、4月の新学期というタイミングを直前に控えているからなんです。
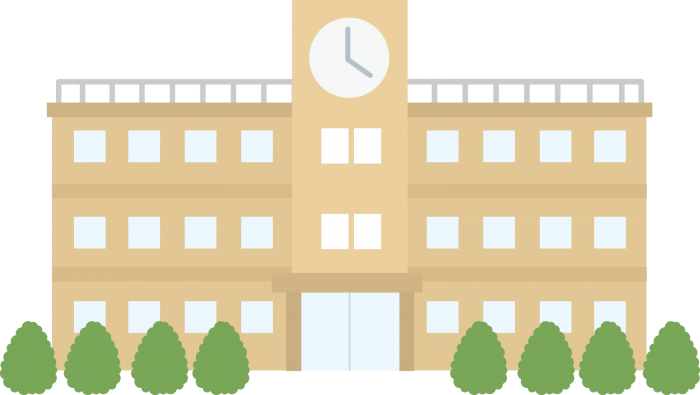
結論から言いますと、4月の進級進学後は、子ども自身も学校への登校意欲が少なからず向上します。
ただ、登校について思ったり考えたりはするものの、それらを上手く整理して行動にまで繋げられるかは難しいです。
そういった時、お母さんお父さんと子どもの関係がとてもよく、話しやすく、自分の気持ちを理解し共感してくれるだろうと子どもが思っているならば、4月というきっかけを、一緒に考えるということが出来ます。
関係性が悪ければ、子どもから相談してくる蓋然性が低くなりますので、ご両親から指示・命令・提案・誘導などをして、子どもがなんとか4月から動けるようにされるかもしれません。
しかし「子ども自身が動かないと、なかなか上手くいかない・・・」と仰られる方が多いので、やはり子どもから気持ちを話してくれたり、相談してきたりすることに越したことはありませんよね。
この時期ならではのコミュニケーションをとって、良い関係性を3学期に繋げる
様々な場面での、親子間のコミュニケーション例を挙げてみました。
①お正月のおせち料理
低学年の子であれば、おせち料理をなぜ作ったのかや、おせちの意味を知ることで、子どもが母親に感謝する気持ちを持つことが出来ます。
②この時期に多い特番などを一緒に見て楽しい時間を共有
親御さんのほうから「去年は色々厳しいことも言ったけどごめんね/辛かったよね/頑張ったよね/楽しかったよね/」等など、感情の共有をしたり、何かを伝える良い機会でもあります。
③大掃除等、家の手伝い
子どもに役割と責任を与え、出来たことには目一杯褒め承認してあげることで、不登校で家にいて普段何もしていない子でも、「俺(私)も家族の一員として認めてもらえるんだ・必要とされているんだ」という、子どもの所属欲求・承認欲求を煽るにもとても良い機会です。
④普段会えない親戚やいとこが集まる場
不登校の子たちはあまり行きたがらなかったりしますよね。そこでただ誘うのではなく、行きたがらなかった場合は、何故行きたがらないのかを考えることが大切です。子どもの第一感情である「寂しい・怖い・辛い・恥ずかしい」等々、そこにどんな気持ちが隠れているのかを親御さんが考え、寄り添ってあげること大切です。
最後に…

不登校支援センターでは、『学校に行く/行かない』というテーマから一旦外れて、まずは親子関係にしっかり向き合ってもらえるようなお手伝いもカウンセリングの中で行っています。
それも我々カウンセラーの役割だと考えておりますので、一度ご相談にいらして頂ければと思います。
関連ワード: 4月 , カウンセラーの役割 , カウンセリング 何をする , コミュニケーション , タイミング , テーマ , プロセス , 不登校 , 不登校 カウンセリング , 不登校 解決 , 不登校支援 , 不登校支援センター大阪支部 , 今出来る事 , 共感 , 受容 , 子どもと向き合う , 家での過ごし方 , 復学 , 感情の共有 , 感謝 , 所属欲求 , 承認欲求 , 振り返り , 新学期 , 新学期からは学校に行く , 第三者の介入 , 考えるきっかけ , 親子間のコミュニケーション , 親子関係 , 適切な関わり方 , 関係性 修復